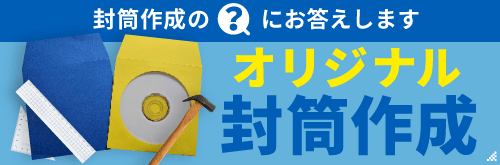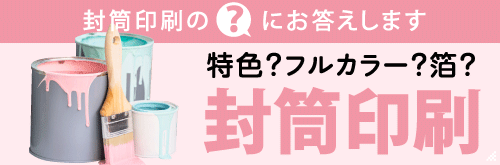お礼・お車代の金額によっての封筒の使い分け
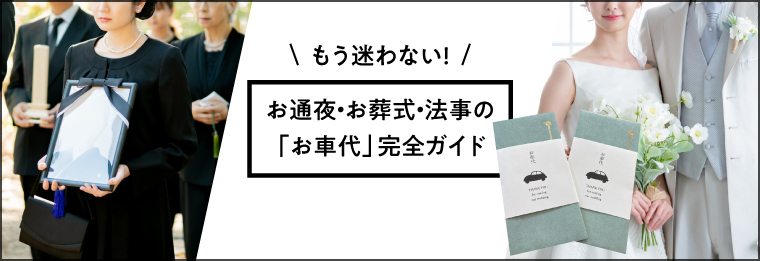
突然の訃報を受け、悲しみの中で準備を進めなければならないお通夜やお葬式。また、故人を偲ぶ大切な法事の席。そうした場で、お世話になった方々へ感謝の気持ちをお伝えする機会は意外と多いものです。
その一つが「お車代」。読経をあげてくださる僧侶の方や、遠方から駆けつけてくださったご親族、主賓の方などにお渡しするものですが、「いざ渡す」となると、
「どんな封筒に入れればいいの?」 「表書きって『お車代』で合ってる?薄墨で書くべき?」 「お札の入れ方にもマナーがあるって本当?」 「そもそも、いくらくらい包むのが普通なの?」
など、次から次へと疑問が浮かんできて、不安になってしまいますよね。
大切なのは、お越しいただいたことへの感謝の気持ちですが、せっかくならマナーもしっかり押さえて、失礼なくお渡ししたいもの。
そこで今回は、そんな「お車代」に関するあらゆる疑問に、分かりやすく丁寧にお答えしていきます!この記事を読み終わる頃には、きっと自信を持って準備できるようになっているはずです。
そもそも「お車代」って何?

「お車代」とは、その名の通り、式場等までお越しいただくためにかかった交通費のことです。僧侶の方にお渡しするほか、遠方から来てくださった主賓や乾杯の挨拶をお願いした方、ご親族などにお渡しするのが一般的です。
交通費そのものを実費でお渡しするというよりは、「わざわざお越しいただき、ありがとうございます」という感謝の気持ちを込めてお渡しする、心遣いの一つと考えると良いでしょう。
【STEP1】お車代の封筒選びのポイントは「シンプル・イズ・ベスト」

■おすすめの封筒
●白無地のポチ袋:
5,000円~10,000円程度を包むのにちょうど良いサイズです。
●白無地の縦長封筒:
お札を折らずに入れることができ、より丁寧な印象になります。特に、お渡しする金額が1万円を超える場合や、目上の方にお渡しする際におすすめです。
●チェックポイント!
●郵便番号の枠がないもの:
郵便番号の印刷がない、真っ白なものを選びましょう。これが最もフォーマルで丁寧です。
●水引は必要?:
基本的にお車代の封筒に水引は不要です。もし水引が付いているものを選ぶ場合は、白黒または双銀の「結び切り」や「あわじ結び」のものにしましょう。「不幸が二度と繰り返されないように」という意味が込められています。蝶結びは慶事用なので、絶対に使わないように注意してくださいね。
私たち「封筒屋どっとこむ」でも、お車代に最適な、上質な和紙を使った白無地の封筒やポチ袋を多数ご用意しております。いざという時のために、いくつかご家庭にストックしておくと安心ですよ。
【STEP2】お車代、これで完璧!表書き・名前の書き方

封筒が決まったら、次は表書きです。ここでもいくつかマナーがありますので、しっかり押さえておきましょう。
●表書き:
封筒の中央上部に、「御車代」または「お車代」と書きます。どちらを使っても問題ありません。
●名前の書き方:
お葬式の参列者に渡す場合は表書きの真下に、少し小さめの文字で施主(喪主)のフルネームを書きます。「〇〇家」と名字だけでも構いません。誰からの感謝の気持ちなのかが、相手にしっかりと伝わります。
●使う筆記用具は?濃い墨?薄墨?:
香典袋は「悲しみの涙で墨が薄まった」という意味を込めて薄墨で書きますが、お車代は通常の濃い墨で書いて問題ありません。感謝を伝えるものですので、相手が読みやすいように、ハッキリとした文字で丁寧に書きましょう。筆ペンや毛筆で書くのが最も丁寧ですが、なければ黒のサインペンなどでも大丈夫です。
【STEP3】お車代、意外と知らない!?お札の入れ方・向き

封筒にお札を入れる際にも、実はマナーがあります。感謝の気持ちがしっかり伝わるよう、ひと手間を惜しまないようにしたいですね。
●お札は新札を用意するべき?
結婚式のご祝儀では新札を用意するのがマナーですが、弔事の場合は「不幸を予期して準備していた」という印象を与えかねないため、新札は避けるのが一般的です。
しかし、お車代は「不幸に対するお悔やみ」ではなく「お越しいただいたことへの感謝」を表すものですので、新札でOKです。とはいえ、あまり気にしすぎる必要はありませんので、新札がなければ、できるだけ綺麗で折り目の少ないお札を選ぶように心がけましょう。
●お札の向き
・お札を入れる向きは、封筒の表面(「御車代」と書いた側)から見て、お札の肖像画(顔)が表の上側に来るように入れます。これは慶事・弔事ともに共通するマナーの一つです。複数枚入れる場合は、すべてのお札の向きを揃えましょう。
細かいことのようですが、こうした心遣いが相手への敬意につながります。
【STEP4】お車代、気になる金額の相場は?

最も悩ましいのが、包む金額かもしれませんね。決まった金額があるわけではありませんが、一般的な相場を知っておくと安心です。
僧侶(お坊さん)へのお車代 5,000円~10,000円が一般的です。もし、お寺から式場までがかなり遠い場合や、タクシーでないと来られないような場所の場合は、少し多めに10,000円~20,000円程度をお包みすると、より丁寧な対応になります。 ※「御布施」とは別にお渡しします。御布施の袋と御車代の袋、もし心ばかりの食事代として「御膳料」をお渡しする場合は、それぞれ別の封筒に用意しましょう。
遠方から来てくれた親族や主賓へのお車代 これはケースバイケースですが、実際にかかった交通費の半額から全額が目安となります。事前に交通手段などをそれとなくお伺いしておくとスムーズです。遠方からお越しで宿泊も伴うような場合には、交通費に加えて宿泊費も考慮し、キリの良い金額(10,000円、20,000円など)をお渡しするのがスマートです。
【STEP5】お車代のスマートな渡し方のマナー

準備が整ったら、あとはお渡しするだけ。タイミングや渡し方にも配慮ができると、より一層感謝の気持ちが伝わります。
●渡すタイミング
・僧侶の方へ:
式の開始前にご挨拶に伺う際か、式がすべて終了してお帰りになる際にお渡しするのが一般的です。「御布施」などと一緒にお渡しします。
・ご親族や主賓の方へ:
お帰りになる直前、ご挨拶をする際に「本日は遠いところをありがとうございました」と一言添えて、そっとお渡しするのが良いでしょう。他の方の目に触れないように配慮することも大切です。
●渡し方
お車代を封筒のまま手渡しするのは、少し不躾な印象を与えてしまう可能性があります。袱紗(ふくさ)に包んで持参し、お渡しする直前に袱紗から取り出して、相手から見て正面になるよう向きを変えて両手で差し出すのが、最も丁寧な渡し方です。
もし袱紗がなければ、小さなきれいな布やハンカチで代用するか、お盆に乗せてお渡ししましょう。
お車代の封筒で、感謝の気持ちをかたちに

いかがでしたでしょうか。お車代に関する疑問や不安は解消されましたか?
●お車代まとめ
- 封筒:郵便番号枠のない白無地
- 表書き:濃い墨で「御車代」、下に施主の名前
- お札:綺麗なお札を、肖像画が表の上に来るように
- 相場:僧侶へは5,000円~、親族へは交通費などを考慮
- 渡し方:袱紗に包み、タイミングを見計らってそっと渡す
覚えることが多くて大変に感じるかもしれませんが、一つ一つのマナーには、相手を敬い、感謝を伝えるための意味が込められています。
お通夜やお葬式、法事は、故人を偲ぶ大切な時間であると同時に、支えてくださる方々への感謝を再確認する場でもあります。この記事が、皆さまの「ありがとう」の気持ちをきちんと伝えるための一助となれば、幸いです。
封筒屋どっとこむではOEMの封筒作成も承っております。「お札がピッタリ入るサイズの封筒」や、ちょっとした金額のお車代にピッタリな「ポチ袋」でのお車代封筒の作成など、お気軽にご相談ください。
封筒作成について
目的/用途からさがす
ビジネスなど各種用途に適した封筒
- 会社用封筒
- 月謝袋
- 別納・後納・受取人払い
- 厚紙封筒(ボール紙封筒)
- ポチ袋
- つり銭封筒
- チケット用封筒作成
- 黒い封筒で高級感やおしゃれな雰囲気を演出
- 窓付き封筒
- 給与窓付き封筒
- 書類送付用窓付封筒
- 健康診断書用窓付封筒
- マイナンバー対応源泉徴収票用封筒
- マイナンバー対応扶養控除申告書用封筒
- レターセットの作成・印刷
- パッケージ用封筒
- マチ付き封筒
- 大型封筒
- 名刺サイズの封筒
- 名刺ときめつけないDE!
- 神社用封筒
- 薬袋
- 案内状・招待状
- 写真用封筒
- 変わった形の封筒
- 宅配用の封筒(マチ付き・緩衝材入)
- DM(ダイレクトメール)にオススメの封筒
- スッと開けTie!ゆめ~る封筒
- 角形ガゼット封筒
- 可能性は無限大‼日本一小さい⁉「プチ袋」
- 透ける封筒
- 透けない封筒
- 正方形の封筒
- ネクタイやお札などを入れる細長い封筒をお作りします。
- レーザープリンター対応窓付封筒(オンdeマド封筒)
- 種袋(種を入れる小さな封筒)